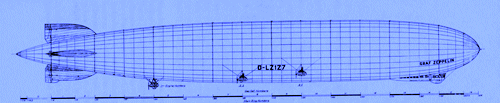
陸を越え、海を越え

Hugo Eckener著 "Im Luftschiff über Länder und Meere"
まえがき(1)
私の回想を綴ったこの本では、ツェッペリン飛行と、それに関する出来事と体験の回想のみを述べようと思う。ここでは、我々がツェッペリン飛行を行ったり、それに尽力したりした時期や、おそらく、航空の長い歴史の中で短いツェッペリンのエピソードと呼ばれることができるであろう時代に限定して記述するつもりである。
それは1924年から1936年にわたる約12年間のことである。
一見、この本は自叙伝のようであるがそうではない。だが私は、この12年間の個人的生活についても記述するように切に薦められた。
私は1868年8月10日、後にドイツ帝国になる北辺の国境に近いフレンスブルクで生まれた。
父はプロイセンのシュレスヴィヒに併合された直後に、ブレーメンからそこにやって来て、さらに広いブレーメンの視野とブレーメンの地場産業であったタバコ製造業を持ち込んだ。母はデンマーク系のフレンスブルク生まれで、その母方はデンマーク領ボルンホルム島の船乗りの家族の出身であった。この家系が私の精神的基底を形成し、次第にコスモポリタンとしての色彩を強めていったのかも知れない。
私は最初に、名門の「市立高等小学校」に行き、その後ギムナジウムに進学して1888年に高校卒業証書を受けた。
残念ながら告白するが、私は学校ではごく平凡な生徒だった。従って、学校時代を思い出すのは別段喜ばしいことでもない。それが学校のやり方のせいだったのか、私自身のやり方のせいだったのか、後になってもよく自問したものである。
なぜならば、既に述べたように、決して精神面で怠慢だったわてではなく、むしろ2~3人の気の合った学友(そのなかには、後に「郷土詩人」となるオットマー・エンキングもいた)と多種多様な知的興味をもって非常に活発に活動していたからである。
私は、そこで純粋哲学を目指すことにした。形而上学と認識論の講義を聴き、論理学、美学その他の学問に励んだ。そのようにして3~4セメスターを過ごしたが、それを学んで実生活で何をするかということについてはっきりとした考えはなかった。
それでライプツィッヒの有名な哲学者ヴントのところに行った。彼はそこに実験心理学の研究所を持っていた。その研究所では、心理学的な問題やあらゆる種類の刺激に対する精神的反応が実験的な方法で調査されていた。
ヴントに、彼の研究生・共同研究者として、その研究所に採用して自分の課題として問題を与えて欲しいと依頼した。
ヴントは本当に私を採用してくれ、私に仕事を割り当ててくれた。私は最後までこの仕事をやり遂げ、それを博士号取得のための「学位論文」にまとめて哲学の専門誌に発表した。
当時、80年代の終わりから90年代の始めにかけて、社会的問題の論究と圧迫が最高潮に達していた。資本についての著書の中でカール・マルクスの書いた教義と政治的要請は、急速な勢いで支持者を獲得していた。ドイツ社民党の成長は驚くべき速さであった。
アウグスト・ベーベルの著書「婦人」や、ベラミーの「2000年を振り返って」、あるいはそれに類する社会構造全体の変革を説く理想主義的な著作は何百万もの読者を得、感銘を与えていた。
私もまたこうした課題の虜になり、形而上学から実践理論的および社会政策的な問題に方向転換し、歴史学と国民経済学の研究を始めた。私はこの分野のジャーナリズムにおいて実行に移そうと本気で考え、博士号の口述試験には、哲学と並行して、特に国民経済学をも試験の学科として選んだ。
それで、場合によってはカナダに行くべきか行かざるべきか迷っていた。そこに予想外の出来事が起こり、たちまちこの問題に決定が下った。期待に逆らって、また私の友人である医師の断固とした意見に反して(私は右膝関節の関節炎で苦しんでいた)、兵役に招集されたのである。
遠く海を越える旅、それは今となっては当然のことながら、とりわけ魅力的なことのように思える。だが、それはこの時に消えてなくなった。
私はまず最初に狭い営庭で執銃訓練をし、痛む膝で(2~3週間の荒治療が必要であった)閲兵式歩調で行軍しなければならなかった。だが、それは私にとっては幸運だったのかもしれない。いずれにせよ、これが私の遠い将来を決定づけることになったのである。
年期を勤め上げ、それに続く第二期予備訓練のあと、私はフレンスブルクに留まり、当時取り組んでいた問題について多くの本を読み、それと並行して、ジャーナリストとしての活動を行っていた。珍しいと思われるものであれば、劇評の中でも書きとめるよう努めた。それは、文学を好む私自身にとっては楽しみとなったが、私がしばしば酷評した作家にとっては、いつも楽しみというわけには行かなかっただろう。
それに加えて、バルト海で何度も長距離帆走を行って、ある程度の航海術の訓練と気象観測の知識を積んだ。それは、後に全く別の分野で役に立つこととなった。
1897年に結婚し、東洋に長い海外旅行をした後、私は大学教授の資格を得るためにミュンヘンに移り住んだ。
しかし、それから間もなくして、健康に配慮し、また 落ち着いて執筆活動を行うためにミュンヘンの住所をフリードリッヒスハーフェンに移した。そこに小さな別荘を手に入れた。
-こうして、私は何も知らずに運命の道をたどることになる。それは、おそらく私の星の中で定められていたのであろう。
当時、私は党の政策にはほとんど関わらなかった。たいていの政治家たちが厳格で、個人的な関心に偏っていることが前々から気に入らなかったからである。
今、私の政治的な信念に関する、いわば棚卸しをしてみたところ、自分がかなり左翼的傾向にあったことが判る。もし、当時の選挙で投票が求められていたら、おそらく社民党に投票していただろう。
カール・マルクスの著書「資本論」は、しばしば奇妙に飾り付けられた文体で、うわべだけの知識をひけらかすような体裁で、根拠の薄弱な教義を演繹的に述べており、言わば資本主義体制の経済活動体系が不可避な機構が現実となり、最終的に大衆の窮乏化を促進させることになり、そのこと自身の結果として「搾取者の強制搾取」をもたらすということを知識として根拠付け、納得させることが少なくなかったので、私は反対しており、いずれその教義は崩壊すると予測していた。
その本は、私が研究した結果によれば、純粋に資本主義体系の機構は1%でも生産の成果から労働者の取り分を生み出す筈であり、その他の要因よりも影響を及ぼすとされていた。
その頃、私は資本の危機を率直に感じて、未完の著書の中から「資本か、労働力不足か?古い問題に対する新しい解答」という表題の1章を小冊子として出版した。
その中で、常に速い速度で展開する好況のなかで、生産を高める幾何学的な尺度によって、労働力の新規採用による創業時の活動は持続しないので、いわゆる「予備軍」として、労働時間の延長や「2交代制」によらなければ、新しく導入された設備を稼働させるには不充分で、労働力の「危機」を招くので、必要不可欠な経営原資の循環が停滞するということを述べた。
ここで、いくらか抵抗はあるものの、一つの逸話を紹介しなければならない。うぬぼれだと受け取られかねないが、やはり私はこの話を紹介しないわけにはいかない。というのも、この中には、私にとって今なお、あるいは今だからこそ当を得た一つの皮肉が含まれているからである。
上述の小冊子が刊行された直後、フランクフルトで開催されたドイツ経済学の学会で、その頃非常に名声のあったフライブルクの経済学者シュルツェ・ゲベーニッツ教授が学会を驚かせた。彼が演台に上がったとき、右手に一冊の論文を手にして次のように言ったからである。
「ここに全く新しい『資本か、労働力不足か?』という表題の論文がある。この論文の著者については、我々はこれからも聴くことになるであろう。彼の名はフーゴー・エッケナーである。」
シュルツェ・ゲベーニッツ氏は確かな予言者であることを実証したのだが、それは彼が思っていたのとは別の形で明らかになった。そうこうしているうちに、私はツェッペリン伯爵と出会い、経済学者ではなく飛行船乗りとして知られるようになったからである。