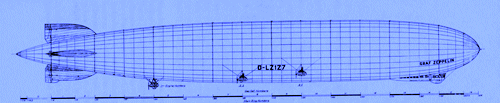
陸を越え、海を越え

Hugo Eckener著 "Im Luftschiff über Länder und Meere"(続き)
世界周航(6)
そこで東に転舵しておよそ1時間飛行したあと、ツングースカ川に出た。そこからヤクーツクを目指して東に針路をとった。
北緯64度線まで北上すると、経線を通過するのがとても早くなり、7時間毎に1時間 時計を進めねばならなかった。このことで船内生活にも相当な混乱が生じた。食事時間の間隔がどんどん短くなりその結果、いつも食欲旺盛であった乗客ですら、飲食を「またか」と怯えていた。
幸いにもこの件で反乱は起こらず、次の日は南に進んだのでその危険性はなくなった。
しかし、別の問題が生じようとしていた。我々は、この地方の何処かに2~3年前に巨大な隕石が落ちたことを知っていた。爆風が大地に途方もないクレーターを穿ち、そのとき吹き飛んだ風であたりの森林の木々をなぎ倒したのである。そのクレーターを飛行船から是非観察し、撮影したいと思った。しかし、残念なことにその正確な位置が判らなかった。乗船者のなかで厳密な位置を知っている人は居なかったのである。
そして、まだ怒っているロシア政府代表は何も情報を教えてくれなかった。それで非常に残念ながら とても興味のある写真撮影を断念しなければならなかった。低ツングースカ川流域に吹く風や旋風は、無限に広がる森林と、所々湿地のある低地を通って、荒涼として単調な北シベリアを吹き抜けて行った。長い距離を飛び続けたが、どこを見下ろしても生命の営みは感じられなかった。
たった1度だけ人間を見かけた。5人いて、筏の上で釣りをしていた。おそらく多数の毛皮猟師が深い原始林に隠れてこの飛行船を見ているのであろう。しかし、こちらから彼らを見ることは出来なかった。
川沿いにも農耕や植林の形跡はなかった。北極海に注ぐシベリアの河川は外部からの関わりを拒んでいた。従って無限の森林資源が使われることなく残っていた。ここで、すべての物が商業世界に取り込まれることを切望しつつも使われることなく朽ちてゆくことを残念に思いながら、この緑の荒野上空を飛び続けていた。おそらく、時が来れば現実となることだろう。
定常的な飛行に変化をもたらしたのは、進行方向に昼前後に現れた、物凄く恐ろしげな雨雲であった。それまで、うまく西風に乗って飛んでいたが、雨雲は両側に数kmにわたって広がり、真っ黒で地表170mにまで垂れ下がり、あたかも飛行船が全く別の天候地帯に入ったかのようであった。この暗く、今にも崩れそうな雲の下にむけて舵をとったとき乱流に巻き込まれてしまった。しかし、大したことはなく、ちょっとピッチングと上下動を起こしだだけであった。驟雨を降らせる雲の反対側には、おそらく-12℃くらいの暖かい気団があり、それに冷たい西風が吹き付けて驟雨前線を生じさせていたのである。空気は非常に乾燥しており、雷雨前線のような乱流が発達しつつあった。ヨーロッパ西岸では、暴風と上下方向の突風を伴う実に嫌な気象の崩れが起きていた。高度1000mの気温は14℃に上がっており、海面レベルの気温は20℃以上であった。夏にシベリアの北緯64度で暖かいことは実に快適であった!
夏に限って言えば、エニセイ川とレナ川の分水嶺はステップに似た台地である。ここに点在する人々の村、ヤクーツクを見た。彼らは滅多に家には住まず、茅葺き小屋の地下に住んでいる。地下への入り口の傍に寝ころんで快適そうに日向ぼっこをしているのを見かけた。この緯度では、冬には零下24~34℃になるので、夏に日に当たることは良いことである。
哺乳類である人類は、食べるものがあれば何処にでも住めるし、エニセイ川とレナ川に挟まれた北シベリアのステップのようなところでも北極海の氷の上でも暮らせる筈であるが、我々はここに住みたいとは思わなかった。
静かで風のない状態で東に飛行し、その間に何もない平原に黄金に輝きながら沈むきれいな夕陽を眺めていた。短い夜のあいだに満月が昇った。いや、少なくとも昇ろうとしていた。南の水平線上に低く懸かっており、大きな黄色い球のように短い軌道をゆっくり移動して行った。北には、水平線の僅か下にある太陽の残光で空は明るく輝いていた。
午後11時、ほかの乗客が寝台に横になって短い休息を取っているとき、1人のアメリカ人乗客が、この舞台の照明のような光景に魅せられてワインを2本注文し、夜を徹して月と薄明るい空を眺めていた。私はしばらく彼につきあった。飛行船に搭載したワインはとても良質で、天空のショウは素晴らしかった。
太陽が北北東から輝きながら昇って朝が来たとき、ヴィルユイ渓谷に来ていた。そこはヤクーツクから560km離れており、そこでレナ川を渡ろうとしていた。ヤクーツクは我々西ヨーロッパの者にはシベリアで最も遠く、殆ど未知な無限の荒野にある町の1つで、地上で一番寒いところだった。ここには数万、いや数百万の流刑者が独裁政権によって通常の罪人あるいは政治犯として送り込まれた。そこでは、もし際限のない苦役や苦難を生き延びたとしてもそこから脱出することは事実上不可能であった。湿地や森林の上を34時間飛行して到達したそこを見て、筆舌に尽くしがたいものがあった。
さらに、同朋である第一次大戦のドイツ人捕虜がここに埋められていた。我々はその墓に花輪を投下することにした。