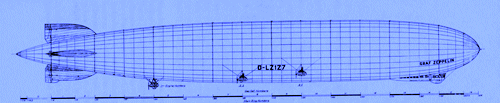
ツェッペリンに捧げた我が生涯

Wir fahren um die Welt
世界一周飛行へ(1)
1929年はじめ、アメリカのハースト新聞が、エッケナー博士に飛行船で世界を周航するという提案を持ちかけた。
飛行船の信頼性と可能性を世界にむけて実証するために、我々はその提案を喜んで受けた。
新聞王ハーストはその飛行の費用の大きな部分を引き受けることになった。
ハーストプレスからは2人のジャーナリストが参加することになり、独占報道権が要求された。それには、さらに条件がついていた。その世界飛行は合衆国の彼らの出発地点、具体的にはレークハーストから出発するという条件である。
我々は当然フリードリッヒスハーフェンを出発地点、目標地点と考えていた。
結局、1929年8月1日に、まずフリードリッヒスハーフェンからレークハーストへ、アメリカから乗船する乗客を迎えに飛び立った。
それはハースト新聞のグレース・ドラモンド・ヘイ女史とカール・H・フォン・ヴィーガント氏、写真家のロバート・ハートマン氏、それに百万長者の後継人ウィリアム・リーズ氏であった。乗客のヒューバート・ウィルキンス卿(著名な極地探検家)、スペインのヨアヒム・リカルド少尉とドイツのジャーナリスト、ハインツ・フォン・エシュヴェーゲ=リヒベルク氏は、既にフリードリッヒスハーフェンから我々と一緒に乗り込み、また引き返してきた。
ジャーナリストと一緒に、乗船料を払った乗客が乗っていた。
世界周航で、上空を飛行することになる国の政府は、それぞれ1人か2人を添乗させていた。
ロシアの地理学者カルクリン氏、日本から藤吉海軍中佐(フリードリッヒスハーフェンから東京まで)、同じく柴田陸軍少佐、草鹿海軍中佐(東京からロサンゼルスまで)、それとアメリカ海軍のチャールズ E.ローゼンダール中佐およびリチャードソン少尉であった。これらの諸氏は 我々と同行することで、彼らの国の上空で困難に遭遇した場合に我々を支援してくれることになっていた。
8月7日、真夜中前にレークハーストを離陸した。
フリードリッヒスハーフェンまで55時間という記録時間で飛行した。
そこで4日間滞留し、その間に飛行船全体 とりわけエンジンの最後の入念な整備・点検を行った。そのほかに飛行船は探検・調査のための資材を運べるだけいっぱい積み込んだ。
8月15日の夜明け前に、先に述べた「アメリカの」乗船客以外の乗船客が乗り込んだ。
ハインツ・フォン・ペルクハマー氏(シェルル出版の写真家)、グスタフ・カウダー博士(ウルシュタイン出版)、ジェルビユ・レアシュ氏(パリの「ル・マタン」)、H.ザイルコプフ博士(ドイツの海洋気象観測所の代表)、クリストフ・イゼリン氏(チューリヒの工場主)、メヒアス博士(スペイン女王の侍医)、マックス・ガイゼンハイナー氏(「フランクフルター・ツァイトゥンク」および「イルストリーテス・ヴォッヘンブラット」)、並びに日本のジャーナリスト北野氏(「朝日」)、圓地博士(「毎日」)の諸氏である。
4時35分、ついに「ドイツの」世界飛行が始まった。飛行船は、青緑色の早朝の空に浮き上がった。素晴らしく美しい日の出を飛行船から眺めることは、乗客にとっても乗組員にとっても初めての体験であった。
ウルム、ニュルンベルク、ライプチヒからベルリンに向かった。
我々はドイツ帝国の首都に別れを告げようとしていた。
そして、熱心なジャーナリストはすでに、始まったばかりの世界周航の記事を投下していた。
ベルリン市民の歓声のうちに飛行船は街の上を2回大きく旋回し、それからシュテッティンを経由してダンチヒへ進んだ。そこは第一次大戦のあと、国際連盟の保護のもとで共和国になっていた。
荘厳なマリア大聖堂が見事な鐘の音でドイツの飛行船LZ127グラーフ・ツェッペリンを歓迎していた。
さらにケーニヒスベルクへ行き、ティルジットで国境を渡り、さらにバルト海岸をラトヴィアへと進んだ。
家屋の建っている場所は、殆どまだ 土と藁で出来た小屋があるだけだった。
休閑地では広大な平野の風景が広がり、さらに飛行を続けてリトアニアの湿地帯を通過した。
当初の計画では、モスクワを通るルートを進む筈であったが、エッケナー博士には、天候のためにその街を北に迂回することが良いと思われた。
しかし我々がモスクワに行くことを届け出ていたので、ロシア政府代表のカルクリン氏は、どんなことがあってもモスクワを目指すように強硬に主張した。
エッケナー博士はその件に関して、そのロシア人をなだめ、何時かソヴィエトの首都に着陸する特別な飛行をすると約束した。
しかしながら、我々は低気圧地域を迂回し、遠い北のヴォログダを越えてウラルのペルミへ航行した。
ウラルは中程度の高さの山岳地帯で、南から北まで長く延び、すっかり樹が生い茂っていた。見渡す限り、森、森、森であった。そして何かものすごいものが見えてきた。大規模な森林火災であった。見渡す限りの煙と炎!
明らかに、そこに消火する人は誰も居なかった。ときどき、我々は濃い煙の中を飛行した。キャビンの中にまで焦げ臭さが入り込んだ。しかし、我々はうまく通り過ぎた。
まもなく我々はウラルの東側に来た -つまり、アジアである!- そしてオビ川に来た。この力強い、激しい源流の大河も、この終わることのない森林にその道を切り開いていた。
オビ川からずっと東に、タイガとツンドラの上空をインバツクの観測所の傍を流れるエニセイ川まで行った。
エニセイ川は北氷洋まで北に流れる第2の大河である。我々は東に広がる下部ツングースカ渓谷を辿った。この渓谷の上空には巨大な厚い雲の壁が延び、突風の発生源があった。我々はその下を通り抜けなければならなかった。
我々はそのとき既に激しい乱気流に捕まっていたが、雲には見かけほどの影響力はなかった。
オビ川からレナ河畔のヤクーツクまで、とてつもなく広い湿地が数千kmにわたって横切っていた。我々はそこで、殆ど終わりのないように見える水面を見た。
それは10m、20m、さらにもっと広い幅で、果てしなく続いて流れる水であった。それはサハラ砂漠の移動砂丘のように、段上になっている水路であった。水の縞条のあいだに、ほぼ10~20m幅の中洲があり、その上には小さくて、ある一定の高さの白樺木立まで繁っていた。
このような地形がどのようにして出来上がったのか、我々には判らなかった。
そこには気の遠くなるような時間があった筈である。
その後もずっと、次第に水や湿原の中に沈んでいった森林が見えた。枯死した木の先端がまだ湿地から突きだしていた。
そこから我々は森林上空を通過し、再び乾燥した大地へと出た。
倒れた木の幹が乱雑に横たわっていた。これを上から見ると、箱から机に放り出されたマッチ棒のようで、その間の空いたスペースからは また大量の原木が伸び出していた。ここでは途方もなく豊かに木材が育っている - だが、人が歩けるような地域ではなく、これらを役立てるために輸送することも出来ないのである。
そこには、直径500mから1000mくらいの丸い湖が数え切れないほど沢山あるのが認められた。まるで大地にコンパスで描いたようにこれらの湖が出来ているのを、我々は理解することが出来なかった。
ロシアの地理学者は、冬に氷と雪が積もって数mの永久氷のレンズが出来、春先にはそれが溶けて大きな氷レンズがそこに残り、軟らかい湿原に沈み、ガラスのレンズのように縁を研ぐのだという。その上に水が溜まり、冬にはまた凍る。氷のレンズはそれ自体、見えなかった。説明を信じるか信じないかは人によるだろうが、あり得る話ではあるように思われた。
航行の途中、北極圏の近くでは一日中明るいままであった。太陽は真夜中に、すっかり平らな北極に輝いていた。
我々は北緯64度まで来た。この飛行区間では、船内時刻を7時間毎に1時間進ませていた。
そうして、常に東に向かって航行していると、乗客は我々同様にシベリアの果てしない孤独に心が締め付けられてはいたが、それにもかかわらず上機嫌であった。
見晴らしは素晴らしく、現実のものとは思えないほどであった。
ただ、一人の乗客だけは、飛行船がこの地域に不時着することを考えて食欲がなくなっていたらしい。この地域に不時着すれば、それは当然、全員が確実に死ぬことを意味していた。誰も救助される可能性はないからである。
一年前にイタリアの飛行船「イタリア」から乗組員の一部を極地の流氷から救出した砕氷船クラシンでさえ、ここで何かが我々の救助に役立つとは思えなかった。しかし、我々の飛行船は順調に飛行し、エンジンは何の障害もなく絶え間なく駆動していた。
しかも、風が有利に働いて、燃料を節約しつつ4基だけのエンジンで航程の大半を進むことが出来た。
しばしば色鮮やかな光景を呈していた湿地帯は、これまで夏に人目に触れたことはおそらく一度もなかったと推測される。というのも、冬はすべての水が凍るので毛皮専門の猟師が徘徊するのは冬だけだからである。
この原始世界を観察し、研究するのに我々の飛行船ほど相応しいプラットフォームなどあり得なかった。
乗客のうち眠っている人が一人でもいたとは、私には殆ど考えられない。
この二度と見ることの出来ない見事な光景を誰も見逃したくなかったからである。
我々はヴィルジュイ渓谷に到達した。そこは次の目標地点であるヤクーツクを流れる激しい大河、レナ川の支流である。
ヤクーツクは、ただ広い地域に小さな木造家屋が点在しているだけの中規模な町である。
我々がシベリアを飛んできたすべての集落には、中央に石垣で囲まれ白い漆喰で塗られた教会があった。
我々がこの開拓集落の上空を飛行し、双眼鏡で先方を見たとき、こちらの方を見ている人影を見かけた。この飛行船を凝視していたのである。
その後、我々がその建屋の真上に来たときには、もう誰も人影はなく -すべては死に絶えたように突然いなくなった- そして、そこを通過してから遙かに振り返ってみたときに、また人々が恐る恐る住居から姿を現して見送っていた。
天空から迫ってくる怪物に、彼らは明らかに恐怖を抱いていた。シベリアには、そのようなものは未だかってなく、それまでほとんど耳にしたこともなかったに違いない。
ヤクーツクでは、およそ摂氏20度のシベリアの夏が支配していた。だが、我々はこの地域の冬の気温が地球で最も低いことを知っていた。
膨大な量の木材がレナの河岸に貯えられており、そこにドイツの標識があった。
ここの冬は厳しいに違いない。
我々はそこにロシア政府の犯罪者が居たと聞いていたが、政治的に好ましくない者を、逃げ場のないこの地域で焼き殺した。それを我々は充分に納得することが出来た。
しかし、それだけではなかった。第一次世界大戦の多くのドイツ戦時捕虜がここで亡くなっていた。
これら国民同胞に捧げようと、我々はフリードリッヒスハーフェンから持参した大きな花輪を、ヤクーツクの小さな墓地にパラシュートで投下した。
そのとき郵嚢を一緒に投下した。すぐに赤い上衣を着た担当がつかみ合いをするようにして受け取った。
この場合、好奇心が恐怖に打ち勝ったようであった。
その郵便物がいつ宛先に届けられるのだろうと思った。
シベリアは広いのである。
我々をオホーツク海から隔てていたのは、遠く延びたスタノボイ山脈の一部であるジュグジュル山脈であった。
広いレナ渓谷を横切って、短時間アルダンに立ち寄ったが、そこには支流マヤが合流しており、そこから曲がってマヤ渓谷となっている。
そこからウイ支流に沿って合流点まで飛行した。
その谷から分水嶺を目指して昇ることにした。
チャートに指示されている尾根の高さはおよそ2000m、峠は約1500mと示されていた。
我々は上へ上へと昇り、峠を見付けることなく最終的に高度1700mに到達した。
まだ更に上昇すれば、浮揚ガスが圧力調整弁を通って流出し、そのためにその後飛行船が海面レベルで着陸することが非常に難しくなったであろう。
しかし幸運にも高度1800mで狭隘な谷の切り通しで狭い通り抜けを見付け、尾根から僅か50mの高さでそこを通過することが出来た。
それは素晴らしい眺めであった。やり遂げたのである。アジア大陸を横断しきったのである。
計算によると、船上にはまだサンフランシスコまで途中無着陸で到達できるだけの燃料があった。
なんと幸運なことであろう!
そうなれば、日本人の失望はあまりに大きなものであったに違いない。
ジュグジュル山脈は、非常に靜で穏やかなオホーツク海に急に落ち込んでいた。
断崖の海岸には多数の小島があり、その上にタルト上のクリームのように霧の海が水平に広がっていた。
ベルリンに別れを告げてから69時間経過して、アヤン港の海岸に到達した。
そこから、大陸とサハリン島の間を通って南にコースをとった。
そこで濃い雲に出遭い視界が妨げられた。
ルートの両側に高い山脈があることを考えると、とても危険な状況であった。
