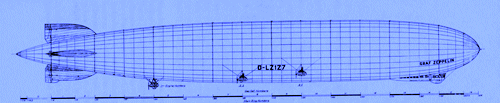
ツェッペリンに捧げた我が生涯

Fahrplanmäßiger Passagierverkehr nach Südamerika
南米旅客定期飛行
20年代の終わりに南米への定期的旅客飛行計画が決まった。1929年10月と1930年4月のスペイン飛行はそれによるものである。
1930年の5月/6月に実施され、南大西洋横断の輝かしい成功を飾った初の三角飛行は、重要な飛行技術、航法および気象に関する知見をもたらした。
それは ドイツ・スペイン・ブラジルを結ぶ定期的な交通運輸がLZ127:グラーフ・ツェッペリンによって実現可能であることを示した。
セヴィリアには繋留柱が建設され、乗客、郵便物、貨物を積み換え燃料を補給するために、飛行船は必要に応じてそこに途中着陸出来るようになった。私は繋留柱建設の現場監督を委託され、1930年の年初にセヴィリアに行った。そこで、ついでに血なまぐさい闘牛ショウを初めて経験した。
ペルナンブコ州の -南米の北東部にある- レシフェには繋留柱が建てられ、水素を生成する小規模なガス施設が建設された。その基地によって、さらに南にリオ・デ・ジャネイロまで(それどころか、その後はブエノスアイレスにまで)飛行を続けることが可能になった。
リオ湾のちょうど背後にあるカンポ・ドス・アフォンゾ飛行場に我々が設置させた小規模な繋留柱「ランデボック」には、我々がそこにいる限り飛行船を繋留させることができた。
こうして、世界最初の飛行船による大西洋横断航空運輸を始める前提条件が整った。エッケナー博士にとって、その飛行船は快適な旅客用飛行船というより、むしろ実験用飛行船であった。我々は、たった20人の乗客しか乗せることが出来なかった。それに対して、乗組員の数は40名とかなり多かった。
数日間にわたる飛行では、3直(海上では、一日に4時間ずつ2回)で、飛行船内の持ち場を担当する。次席航海士から無線通信士、操機手、気嚢主任という具合である。実際の旅客用飛行船の運用は、LZ129およびLZ130で初めて実現できると我々は想定していた。ところが、グラーフ・ツェッペリンは、8・3/4年の現役期間を通じて13110人もの有料乗客に、非常に高い満足感を与えて運航したのである。
1931年8月29日、その年の最初の3回にわたる南米飛行が運航スケジュールに基づいて満席で開始された。それによりDELAGは大西洋を越えて郵便および旅客運送を始めたのである。
その4年前には、あのリンドバーグが飛行機で初めてニューヨークからパリまで単独飛行し、フランス人コストとルブリがセネガルのサン・ルイからブラジルのナタールまで南大西洋2950kmを無着陸で飛行し、3年前にはケール大尉、ヒューネフェルト卿とフィッツモーリス大尉が、初めてアイルランドからニューファンドランドまで北大西洋を東から西へ直接横断する3400kmの長距離飛行を行っている(1930年はじめに再度実行されている)。
しかし我々は、8000km(フリードリッヒスハーフェン・レシフェ間)、あるいは6300km(セヴィリア・レシフェ間)の距離を越える旅客定期運航を始めたのである。
次いで1936年5月6日、LZ129ヒンデンブルクは北大西洋航路の定期運航を始めた。1938年8月に、一機のフォッケ・ウルフ200「コンドル」が、ベルリン-ニューヨーク、ニューヨーク-ベルリン間の世界記録飛行を打ち立て、大西洋横断飛行機旅客運送の可能性を示し、それは1939年の夏にパン・アメリカン・ワールド・エアウェイズによって開始された。
LZ129がレークハーストで炎上し、旅客飛行船運航が終わった1937年5月までに、グラーフ・ツェッペリンは63回、ヒンデンブルクは8回の南米飛行を行った。
1936年には絶頂期に達し、南米飛行が20回、北米飛行が10回行われ、従ってこの年は2隻の飛行船による旅客運送飛行は大洋を60回も、それも異常な悪天候にもかかわらず横断したのである。1936年の飛行時間は、リオ・デ・ジャネイロへの往路で83~114時間、復路は91~127時間であった。最初の年は飛行時間が長かったが、それはレシフェにおけるガス充填に多くの時間を要したためであった。
乗客はリオへの飛行に1500ライヒスマルク、往復では2700ライヒスマルクを支払わなければならなかった。運航時刻表はHAPAGと共同で前もって確定されており、HAPAGは代理店でも我々の乗船券を販売していた。
1935年4月2日以降、我々はもはや伝統的なDELAGの旗の下では航行しなかった。そこには国家の管轄下のドイツ飛行船運航社(DZR)が新たに設置された。1936年5月11日になってようやく、南(北)米飛行は、フランクフルト・アム・マインに新たに建設された空港(ライン・マイン空港)で発着することになった。最初の5年間はフリードリッヒスハーフェンを起点にしていたのである。我々はそこから、スイス連山に沿ってバーゼルに行き、バーゼルからリヨンへ、そこからローヌ渓谷を下った(そこは撮影禁止であった)。
ローヌデルタから地中海に行き、ピレネー山脈の東端であるクレウス岬を通過してバルセロナを越え、スペイン東岸を南下した。
乗客はその旅を楽しんだ。沿岸の古くからの漁村や、乾燥した連山の枯れたような植物やみすぼらしい街路、上空から見ると大層荒廃した印象を与える地域を、乗客たちは乗客用ゴンドラの大きな窓から、視界を遮られることなく眺めていた。それだけに、海岸そのものや地中海の水の眺めは大変美しかった。それは素晴らしい色彩の戯れであった。
ヴァレンシアの手前では、眼下に古代ローマのサグント城塞を眺めることもあった。気象状況によっては、デ・ラ・ナーオ岬、あるいはバレアレス諸島の西のイビサ島に寄ることもあった。スペインの南部海岸は多くの場合、非常に強い西風が吹いておりジブラルタル水道を抜けて大西洋に出るために、さらに南下してアフリカ海岸を航行せざるを得なかった。地中海の西部に小さなアルボラン島があった。それは非常に小さく、殆ど知られていなかった。しかし、その島は航海上では高い価値があった。大きな燈台がそこに建っていたのである。
我々は夕刻には大体いつもフリードリッヒスハーフェンに居たので、午前中にはスペイン南端に接近した。乗客はくつろいで腰掛けており、窓は開放され、下方の視野を遮るものはなかった。人は隙を持て余し、そこら中を眺めていた。飛行機では、すべてがとても速く、飛行高度が高いと、小さな丸窓からの視界はかなり制約されていた。
乗客は朝食後にグリーティングカードを書いていた。多くの人が、グラーフ・ツェッペリンで喫煙出来ずに苦労していた。その飛行船には、まだ喫煙室はなかったのである。だが、それは多くの乗客の健康にとって唯一の障害であった。
ジブラルタルの堅固な岩壁は、いつ見ても印象深い景観であった。空からは、セメントで固められた明るい平地が目立ち、そこには雨水が溜めてあった。ジブラルタルには井戸がなかったのである。さらに対岸に沿ってタンジールまでで最初のアフリカの街セウタがあった。その当時はまだ、国際的に知られた街であった。我々はよく、ちょっとした寄り道をした。上空から見たこの港町に、とても興味をそそられたのである。まもなく、我々はスパルテル岬で海へ出た。アフリカの北西端である。そこには大きな無線塔と燈台が建っていた。監視人はいつも我々の到来を喜び、霧砲を何発か発射した。
そのような燈台やその他の特徴ある場所で、位置と時刻を正確にログブックに記入するために、我々はそれらの方位を光学式測定器で測定した。
位置、速度および偏流の測定は航海術の基本であり、無線方向探知と、必要に応じて天文測位により補正を行う。
あるとき、我々が大西洋上にいたとき、うまくいったことがあった。南西方向の北東貿易風が追い風になったのである。この穏やかな航区で、後に組み込まれた自動操縦装置は非常に有効であった。それは羅針儀によって操縦されたので、方向舵手はその主要な仕事から免れた。昇降舵については、そのような自動操縦を組み込むことが出来ず、その代わりに押しボタン操舵だけを設置した。そうすることで、方向舵輪を廻す必要はなく、ただ2つの押しボタンを操作するだけで良くなった。
大西洋上では、とても暖かかったので乗客は上着を脱いでいた。殆どの航行は、カナリア諸島と西アフリカ海岸のあいだを行くか、あるいは直接フェルゼン諸島上空を飛行し、しばしばラスパルマスの上をヴェルデ岬諸島まで航行したが、その小さなフォゴ島にある最も高い山ピコは海抜3000mで、そこがこの飛行のハイライトであった。
広い大西洋上で汽船と遭遇したときは、乗客はいつも大層喜んだ - しかし、もっと喜んだのは、人気のない海を長期間航行してきた後に飛行船との遭遇を体験することが出来た大型船の乗客達であった。
客船の船長は、我々がその航路の近くを航行していることを知ったときには、大抵無線を寄こした。「うまくこちらへ舵をとれ!我々の乗客に見せてあげてくれ!」汽船が我々の航路からそれほど離れていないときには、我々はいつもそれを行った。彼らはとても喜び、サイレンを鳴らして挨拶をした。我々は大抵、後方からおよそ高度50~100メートルまで接近した。
我々の飛行船は、しぶきと波泡が覆う荒天の海にしばしば遭遇した。そのときデッキで我々を見ていた乗客はおそらく10分の1くらいで、あとの人たちは、おそらく船酔いのためキャビンで横になっていた。そして我々の乗客は、開かれたキャビンの窓辺の手摺りにもたれて、手を振りながら素晴らしい光景を味わっていた。
(大西洋航程のおよそ3分の2あたりの)小さなセントポール岩礁を除けば、我々が定期的に上空を通過した最初の陸地は、南米の北東端からおよそ350km手前にあるフェルナンド・デ・ノローニャ島であった。ブラジルはこの島に政治犯を拘置していた。当時、ブラジルでは毎年のように反乱が起こり、囚われた者達がフェルナンド・デ・ノローニャに送られ、次の年には連れ戻され、その年の逮捕者と交替させていた。毎年、そんな風に行われていた。
我々は3時間後に、ナタールからレシフェまでたどった海岸に到達した。
至るところが湿地で、僅かにレシフェの北に丘が延びており、そこには沢山の教会や修道院が建っていた。レシフェも湿地と沼に囲まれており、人はそれを「ブラジルのヴェニス」と呼んでいた。街は枝分かれして広がっていた。貧しい住民はとても原始的な生活をしており、杭を打って板と葦で壁を作り、屋根は椰子の葉か缶詰の缶であった。住民のなかには多くの有色人種がいた。そこはまさに、ブラジル中の混血が集まる場所であった。
フリードリッヒスハーフェンあるいはセヴィリアから最初の中継点であるレシフェ上空では、我々はいつも着陸前に何度か旋回した。発着場上空で、飛行船は高度40~50メートルで静止し、バランスをとって着陸索を投下し、地上要員がそれに飛びついて飛行船を引き下ろした。
乗客はそこで降りることが出来、それから地上支援員はグラーフ・ツェッペリンをゆっくり慎重に繋留柱まで曳いて行き、飛行船の船首を繋いだ。
飛行船先端の繋留用コーンが繋留柱に取り付けられ、それに合う漏斗にカップリングされ、船体は風が吹くと風見のように方向転換することが出来た。
(飛行船船尾の最も低い位置にある)後部エンジンゴンドラは、マストのまわりの環状レール上を動くことの出来る台車に固定された。それによって船体は、どこから風が吹いても常に風の方向に向くようになった。
それから手荷物、郵便物、貨物が積み換えられた。ときどき我々は、さらに小型飛行機あるいは自動車を貨物として搭載した。我々は一度、ドイツ人女流飛行家アントニー・シュトラスマンのスポーツ機をレシフェで下ろし、すでにその2時間後には、彼女はそれで南方へ飛び立ったのだった!
飛行船には浮揚ガスと燃料ガスが補充され、ガソリン、エンジンオイル、水も補給され、新鮮な糧食が積み込まれた。たいてい、それにはその日の残りの時間と一晩を要した(もっとも、最後には4時間で済んだが)。
外のキャビンの柵には、下船した乗客の重量の代わりになるようにセメントブロックが吊り下げられ、飛行船は常にきちんと釣り合いをとっていた。
我々の途中着陸はいつも、当然のことであるがペルナンブコの人たちにとってお祭り騒ぎとなった。まるで、いつも祝祭日のようであった。群衆は飛行船を見るために、そして出来ることなら内部設備を見ようと駆け寄ってきた。ブラジルの巡査はタラップに立って、野次馬が中に入るのを押しとどめていた。
乗客と乗組員は、そのあいだに街を見に行った。街は当然ながら、あるものすべてを訪問者たちに見せて歓迎した。アトラクションの一つは、とある広場の大きな水槽に入った海牛(ジュゴン)であった。観客に大きくぎこちないその動物がよく見えるように水槽の一部から水が抜かれた。当然、それは海牛には良くなかった・・。
飛行船に燃料を補給し、満載にしたあと我々はさらに南に向かって出発した。我々はリオ・デ・ジャネイロの東岸をたどった。本来、この航程には16時間しかかからない。しかし、我々はレシフェを朝離陸し、翌朝リオに着陸したかったので、この大変美しい区間に24時間滞在した。その先の航区の大部分では -ここでは追い風に恵まれることが多かった- 2基のエンジンを停め、動力を半減して航行した。眺めは素晴らしかった。長く直線的な航行で、砕ける波の白い縞の浜と水面を我々の飛行船の黒い影が滑った(ところで、影がくっきりとした線を描く時間から、飛行船の速度を楽に決めることが出来る)。この海岸では座礁した多くの難破船を目にしたが、そこには誰も居ないことは明らかであった。
バイア(現在のサルバドール)は見応えのある景観を呈していた。この街は、広く鮮やかな湾と大洋との間の小高い丘の上にあった。港の中央には、かつてポルトガル人が建てた砦があった。湾のはずれのサン・フェリックスには、世界に知られた2つの葉巻製造企業、スエアディックとダンネマンの工場があった。さらに行くと、海岸線に沿ってイルホイスとベルモンテがあった。ここにはカカオが沢山植えられ、積み出されるところである。レシフェとリオ・デ・ジャネイロとの区間の中ほどの南大西洋には、2つの立派な島「ドス・イリオス」があった。この島は絵に描いたように美しく、殆ど自然のままの状態であったので、私は特に気に入っていた。その島には7本の椰子と、2つの石造りの家とひとつがいの山羊だけがいた。素晴らしい砂浜がその島を縁取っていた。
その島を見るたびに私が感動していたので、何にでもすぐにぴったりの名前をつける方向舵手のシェーンヘルは、この島を「ザムト島」と名付けた。ある航行でエッケナー博士が乗船していたとき、その島に近づいてシェーンヘルが大声で「ザムト島に来たぞ!」と大声で言った。それを聞いてエッケナー博士が飛んできて「どれがあなたの島ですか、ザムトさん?」と訊ねた。
フリオ岬をまわると - まもなくリオ・デ・ジャネイロが見えてきた。右にはグアナバラ湾の河口でリオの天然の港であり、左はコパカバーナの街で、その華やかな海岸通りに多くのホテルや有名なビーチがあり、その中ほどに「砂糖パン」岩塊があった。空から見るリオは、言葉で表せないほど素晴らしい光景で、一般の旅行者はその砂糖パンやコルコバドからも、その眺めを楽しむことが出来た。だが、我々の乗客が見たのは、どれほど魅力的なものだっただろう。同じくらいの高さからではあったが、パノラマは絶えずゆっくり変化し、彼らはその光景を自分自身の中に刻み込むことが出来たのである。
我々は順調に湾内に入港し、砂糖パンを一周し大都市を観察した。コルコバドの丘の上では、その街を祝福するように高さ32メートルのキリスト像が両手を広げていた。
夜、街の灯火の輝きでこの立像が明るく照らされているときも、あるいは朝日に照らされて建物の上に立つときも、圧倒的な美しさであった。
最初の数年、我々は湾の後方のカンポ・ドス・アフォンゾ飛行場を着陸地点としていた。しかし、湾にはよく霧ががかるため不便であった。我々はその場所を見付け出すのにたびたび苦労した。その後、リオの南およそ60キロ地点にあるサンタ・クルス・デ・セペティバに堅固な近代的格納庫と移動可能な繋留柱、ガス施設、燃料貯蔵庫、およびそれに連絡する引き込み線が設けられ、1936年夏以降利用可能になった。それから、我々は2~3日リオ・デ・ジャネイロに滞在できるようになり、レシフェの中間着陸を短縮することも可能になった。
LZ129:ヒンデンブルクでは、私はすべての飛行で首席航海士として乗務したが、その間の8回の南米飛行で、レシフェに中間着陸したのは2度だけであった。
そのほかの14回の飛行では、フランクフルトからリオまでの1万kmの距離を無着陸で航行した。この飛行船着陸場ができるまで、我々はいつもリオのランデブロックで短時間のみの中間着陸をした。燃料補給は行わず、郵便物、貨物と乗客だけを乗せ替えて、その後すぐにグラーフ・ツェッペリンはレシフェに向けて出発した。
1934年6月の終わりに、我々はリオからモンデヴィデオを越えてブエノスアイレスまで往復する連絡飛行を行った。それは、我々の南米航路をアルゼンチンまで延長する計画に基づいたものであった。エッケナー博士はこの飛行によって、ウググアイとアルゼンチンで飛行船を見せると同時に、気象学的状況の調査を意図していた。この海岸の飛行ではパンペロが非常に懸念された。ここでは、突然陸から海に向かって暴風が荒れ狂うことがあるのである。事実、我々もパンペロで飛行船を激しく上下に揺すられながら、突風前線とそれに続く南西の暴風を乗り切ったことがある。
我々はリオ・デ・ジャネイロから海岸に沿って、ブラジルの南の州へ向かった。サンパウロと、ブルーメナウのような、非常に沢山のドイツ人入植者が住むサンタカタリナ州の上空を飛行した。上から見下ろす景色は素晴らしいもので、ドイツと同じように作られた小さな村や町が見えた。我々の飛行船が上空に姿を現したとき、この植民地の人々はどれほど喜んだことだろう!
ポルトアレグレとリオグランデを過ぎて、我々は夜中にモンテヴィデオに到達し、そこから明るくなる前にリオ・デ・ラプラタに行った。
素晴らしい朝であった。新鮮な風が吹き、野には僅かに霧氷があった - ちょうどドイツの5月の朝のようであった。8時にブエノスアイレスに順調に着陸し、我々のために普段よりも早く起きた住民たちの嵐のような歓迎を受けた。
我々は乗客と郵便物を載せ替えて復航に出発し、この上なく美しい海岸線に沿って再びリオに向かった。
レシフェは、気象学的環境が非常に好条件であったので我々にとっても理想的な拠点であった。そこでは雷雨や暴風は殆ど起こらなかった。 -もっとも 時折、短時間に強い熱帯雨のとてつもない水塊が天から降ってくることはあったが・・。
あるとき、リオからの帰りにそこに着陸しようとしたときも、巨大な雨雲が掛かっていた。
着陸時、我々はその上空を飛行せず、地上要員の上空で静止状態になるように、常にエンジンを停めなければならなかった。そうして我々は、その地点の上空で適切な高度になるよう、上空で水平飛行をし、徐々に降下したが、そのとき突然の熱帯雨に見舞われた。一瞬に、おそらく6トン、それどころか10トンもの雨水が飛行船に降りかかり - 我々はもう殆ど飛行していなかったため、飛行船は物凄い力で押し下げられた。昇降舵を動的に作動させることは、もはや不可能であった。我々に出来るのは、着陸の際に飛行船がなるべく前進しないように、エンジンを逆転させて飛行船を後進させるよう切り替えることくらいであった。
だが飛行船が停止する前に、後部エンジンゴンドラが地面に接触し、そのまま滑走してしまった。乗務技師のザウターと操機手ダンゲルが、飛行船を軽くするためにそのゴンドラから飛び出して、その後を追った - およそ100メートル走行したのち、やっと停止した。
我々は、ある集落のなかに着陸した。その一帯の至るところに粗末な小屋が建っており、そこに我々の飛行船が衝突し小屋の一つに胴体がのしかかった。ダンゲルには、その小屋で主婦がコーヒーか何かを火にかけているのが見えた。
飛行船は非常に燃えやすいので、彼は瞬時に危険を察知し、あっけにとられた住人を尻目に、火にかけてあったスープ、それから水と土をかまどの火の上にぶちまけて消火した。
短い土砂降りのあと、外ではもう日が射しており、飛行船の表面に溜まっていた雨水は蒸発し、滴下していた。次の瞬間、飛行船が再びとても軽くなったので、ひとりでに上昇し始めた。
操機長のレッシュが「急いでゴンドラに乗れ!」と叫び - ザウターとダンゲルは全力で、再び飛び乗った。
乗客も、グラーフ・ツェッペリンが墜落したことに気づいて降りる準備を始めた。ヘッドウェイターのクービスはとても機転が利いたので、「お客様方、これは予備着陸です。本着陸はもうすぐ行われます。」と言って押し留めた。
小屋の持ち主は小屋の修理代を受け取り、驚かせた償いとして500ミルライスの金を受け取った - 当時およそ60マルクに相当する。その後、彼は長いこと毎日教会で蝋燭を供えて、飛行船が再び屋根の上に降りてきてくれるように祈ったという話である。
復航では、目の前に広がるフェルナンド・デ・ノローニャ島を囲む、緑の海に黄色と赤の岩塊と岩礁、その上にまた緑という素晴らしい色彩の戯れを再び目にすることが出来た。その島には信じ難いほど険しい岩山がそそり立ち、「神の親指」と呼ばれていた。
アフリカ西岸では北東貿易風が特に強く、我々の帰航が妨げられる可能性があったために、西方に迂回し、北東に航くのではなく殆ど北に進まざるを得なかった。
その後我々はモロッコと同緯度のマデイラに到達した。そのため、我々はそれほど長い間北東貿易風と闘う必要はなかった。大西洋のずっと外側では風力は弱く、我々は迂回したにもかかわらず早くヨーロッパに着くことが出来た。これは、言うならば「気象学的航行術」とも言うべきもので、それは飛行船には好都合であった。飛行船の場合、飛行機のように天候に関わりなく直線的な連絡ルートをとるのではなく、たとえ距離が長くとも時間と燃料を出来るだけ節約するような風を利用する進路がとられた。
マデイラから、中間着陸を行うためにセヴィリアに向けて、我々は北東にコースをとった。その必要があったのである。我々は強い向かい風で燃料を使い果たしており、繋留柱で1トンあまりのガソリンを補わなくてはならなかったのである。ほとんどの乗客も、そこで乗下船することになっていた。天候が幾分持ち直したので、我々は南東スペインを海岸線に沿うことなく、ピレネー半島を斜めに横切って一周し、マドリッド上空を横切り、そこで郵便物を投下した。
バルセロナからピレネー支脈の玄武岩塊を越えて、ローヌデルタに行き、そこから渓谷に入った - たびたび、ミストラルに阻まれ苦労した。ときおり、我々はそれを通り抜けるために長時間苦闘した。
フリードリッヒスハーフェンに着陸する前に、しばしばツェッペリン村の上空で2~3回凱旋旋回を行った。そこは、当時すでに社会福祉的な考えを持っていたツェッペリン伯爵の提案で、飛行船製造社で働く工員や職員のために、経営者コルスマンの指揮のもとでツェッペリン・コンツェルンによって建設されていた。それは農場と酪農工場も兼ねており、全従業員の食糧の供給を行っていた。
地元の人や、とりわけフリードリッヒスハーフェンやその周辺を夏に訪れる人が飛行船の帰港を知ると、いつも祭りが行われ、飛行船製造社のまわりには人が集まった。我々は、地上の風向きを示すために掲げられた州旗の上空に進入した。我々はつねに、舵効きが良くなるように風に向かって航行した。グラーフ・ツェッペリンは繋留柱に曳航された。その左右には軌条が固定され、格納庫の中に運び込まれた。そこで乗客はゆっくりと下船することが出来、手荷物、貨物、郵便物の荷降ろしも妨げられることがなかったからである。
一度飛行船で旅行した乗客は、繰り返して乗船した。乗客は、我々の南米 後には北米飛行における信頼性と時間の正確さに感激した。ブラジルでは我々が到着する時刻が原住民に知らされ、それによって彼らは食事の時間を決めていたそうである。我々の乗客は、飛行船の航行は他のどの交通手段より楽だと感じていた - 速さだけでなく、航行の静かさや振動においても、快適な水上船舶よりも我々の方がはるかに優れていたのである。ハンブルクからニューヨークへの汽船では、悪天候になると、どれほど頻繁に乗客たちはベッドで横になったり、気分が悪くて下船したりしたことであろう。我々の飛行船では、乗客が船酔いになることは決してなかったのである!