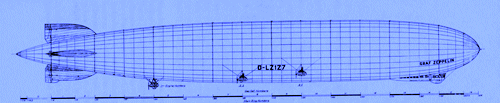
ツェッペリンに捧げた我が生涯

So überlebte ich den Brand des Luftschiffes HINDENBURG
こうして飛行船ヒンデンブルクの火災を生き延びた
1937年5月6日の午後、ニューヨークに到着した。
マックス・プルス船長が指揮をとり、エルンスト A.レーマン船長とアントン・ヴィッテマンが乗客として乗船していた。
その飛行は定常通りに進行していたが、向かい風のために航行時間が延びており、そのため計画通り午前中に着陸することは出来なかった。着陸には都合の悪い真昼時を避けようと、乗客のために飛行船からニューヨークの展望飛行を行った。
15時にレークハースト近くの飛行船発着場に着陸するために、そこに向かった。
しかしレークハースト上空は土砂降りだったので、着陸地点上空を離れて再度海上に向かった。雷雨前線が再び北西に移動して海上をさまよい減衰してゆくのを認めながら外海を航行していた。海上は低温で安定しており、そこでは乱流や上昇気流は発生しないため、海上での障害はすぐに解消されるであろうと期待した。
発着場司令のチャールズ E.ローゼンダールは、発着場の荒天は去り着陸可能な天候になったと、17時12分に無線通信で伝えてきた。
16時から20時に割り当てられていた私の当直に就く前に、私はメモ帖を持って船内を歩き、バラストの残量と飛行船の長さ方向の分布状況を自分でチェックしていた。
飛行船は北大西洋を渡航中に25~30トンの燃料を消費し、したがってそれだけ重量が軽くなっていた。飛行船が航行しているかぎり、飛行船の長さ方向の傾斜により、つまり昇降舵の傾斜あるいは適切なバラスト配置によって、飛行船の上昇を抑止することが出来た。着陸するためには、飛行船の重量を出来るだけ精度良く何度も計測する必要があった。
上昇するにしても下降するにしても、着陸は離陸と同様に「静的」に行う必要があった。これはバラストあるいはガスの放出によって行われた。その上、空中で水平状態を維持しておかねばならず、この「トリミング」を達成するために、バラストを移送し、必要であれば飛行船の然るべき個所からガスを放出するか、バラスト水を投棄する必要があった。
私の巡回中に40番リングに -つまり飛行船のずっと後方に- 8~10トンの水があるのを見た。私はガス嚢担当のクノールに聞いた。「これは一体どうしたんだ?」彼は答えた「はい、水を後方に送るよう前から命じられました。」それに対して私は指示した「前方の60番リングにさらに1トン、それからずっと前方の2つのバラストホーゼを満載!」
それらが実行されることを私は確信していた。ガス嚢主任は最も信頼できる人物だったからである。そのあとで私は一等航海士として当直を引き継いだ。私は、こうして着陸操船の指揮を執ることになった。
我々は、またレークハーストに引き返した。前線は雲の姿がちぎれて弛み -我々はヒンデンブルクを操縦して濃い灰色の雲の立派な門を通過した。そうして前線の裏側に行き着いた。まだ雨は少し降っていた。風は常に方向を変えて、嵐のあとあちこちと不安定であったが天候は着陸には全く申し分なかった。飛行船の重量を測定して、所定の場所の少し前で停止するまで速度を落とした。燃料を消費したため、飛行船全体が軽くなりすぎていた。軽すぎる飛行船は船首を下げて降下する傾向がある。当直前任者はこれを予見して、大量のバラスト水を40番リングの後部からポンプで排出していた。
しかし、いま飛行船は強風にあおられていることが判った。その結果、船尾が重すぎて少し下がっていた。こうした理由から、我々は前の7つのセルからガスを排出した。水素1立方メートル「放出」するたびに飛行船はおよそ1kg重くなる。
それで我々は長い時間かけて、飛行船が均衡を保ち、およそ高度100メートルで移動していない状態で水平になるように調整した。そのあとでゆっくり繋留柱に移動して行った。しかし、その間にまた風が舞ってきた。従って我々は大きな鉤を投下しなければならなかった。つまり、左舷方向に逸れなければならなかった。そして、飛行場の社員食堂と士官宿泊所の上をすばやく通り過ぎ、風に逆らって再び繋留柱に近付くことが出来た。
およそ1キロメートル -ほぼ飛行船長さの4倍- 繋留柱から遠ざかったとき、飛行船の後方がまた重すぎることが明らかになった。私はそこで300kgのバラスト水を投棄した。すべてが機能していることを確認するために、私は指令ゴンドラの窓から身を乗り出した。そして、水が60m下に噴出して地表に落ちるのを自分の眼で見ることが出来た。私はその瞬間、雷雨の中でこの噴出では電気的放出が出来ないのではないかと気になった。しかし何事も起きなかった。
最微速でさらに進み、前部エンジンは既に停止していたが後部はまだゆっくりまわっていた。これから、この2基も停止した。飛行船は非常に僅かではあったが着陸地点に向かって漂っていた。私は前部エンジンを再度短時間作動させ、しかも逆転させることによって完全に停止した。
着陸地点からおよそ600メートル離れたところで、飛行船の後部がまた重くなっていた。それで、また300kgのバラスト水を投棄した。それで飛行船は再び完全にバランスが取れ、ちょうど地上支援員の真上、高さ60メートルに来た。
しかし、その後またすぐ飛行船が重くなりすぎたため、私は水を500kg投棄した。
それから我々は、完全に静止しバランスを取っていた。
いまや、我々は仕事をやり遂げた。プルス船長、レーマン船長と私は窓に立って地上支援員の操索の一部始終をゆっくりと眺めていた。
繋留索が降ろされ、発着場にいた熟練した従業員が我々を引き下ろさなければならなかった。突然、我々は飛行船に衝撃が走るのを感じた。我々は見渡して訊いた。一体何が起きたのだ?
ひょっとして繋留索が切れたのか?
外を見たが索はゆるく下に垂れており、それが衝撃の原因であるとは考えられなかった。一体何だったのか?我々の横には格納庫の大きな入り口があり、部分的にガラスが嵌っていた。そして、そのガラスに火が映っているのを眼にした。同時に誰かが叫んだ「飛行船が燃えている!」
安定鰭近くの上で火が噴き出したので、我々はそのとき操縦ゴンドラからそれを直接視認することは出来なかった。しかし、すぐに飛行船の後部が沈下したことに気がついた。2等航海士のハインリヒ・バウアーが私に「バラストを投棄しますか?」と訊いた。 - それは飛行船乗りの真っ当な反応であった。私は「いや!出来るだけ早く降りろ!」と叫んだ。飛行船はそのあいだに45度に傾いていた。船尾では、まずガスに火がついていた。
燃え上がる骨組みが、すぐに全部地面に衝突して壊れた。我々は最初、飛行船がもっと急激に傾き、我々は船尾の火の中に落下してしまうのではないかと不安を抱いた。しかし、火は中央通路を通って急速に前に広がり、そのため船体前部も急に沈下を始めた。レーマン船長が叫んだ「各自、窓を探せ!」。
次のような考えが、脳裏をよぎった。もし飛び降りるのが遅すぎれば、操縦ゴンドラの中にいる限り、燃えさかる飛行船の前部がおまえの上に襲いかかってくる - だが、早すぎれば足の骨を折り、船体の骨組みが落ちてきたときに逃げられなくなる。
船体前部が跳ね上がったとき、プルス船長と私は、航海室の窓から5m近い高さを飛び降りた。ぎりぎり、何とか間に合った。私は地上の多くの人の上に着地した。プルスは方向感覚が混乱し、炎の燃えさかる方向に走り戻った。
彼が炎の中に姿を消すのが見えた。私は立ち上がって側方に走って逃げようとした。気ばかり先走って身体がついてこられなかった。
同時に骨組み全体が我々の上に崩れ落ちてきた。あまりの熱さに私は立っていることが出来なかった。未だそこらじゅうが燃えているのに、私は地面に倒れた。ガスの火は多くの酸素を使い果たし、吹きつけてくる風はシューシューと音を立てていた。
突然、煙が地面から一斉に湧き上がった。私は、目の前で電線と担架がめらめらと燃え上がるのを見た。今はもう、じっとしていてはいけない!と思った。
私は自分の手でその瓦礫を押しのけ、灼熱したがらくたを取り払った。
今日でも、まだ右腕に大きな火傷の跡が3つある。
しかし -ありがたや- 私は身動きがとれた。さらに残骸の脇を20メートル先へと走った。当然ながら私の制服は激しく燃えていた。私は湿った草むらに飛び込んで、砂地に身を投げ転がった。
立ち上がり、それから残った火を叩き消して、初めて片眼を閉じて、それからもう一方を閉じた -目が見える!- 耳に手を伸ばすと、それはまだそこに付いていた。幸運なことに、正面の帽章は逃げているあいだにぼろぼろになっていたが、制帽は頭に載っていた。私は制帽を深く耳の上にかぶっていた。それは私の眼と耳をしっかりと保護してくれた。 - それがなければ、私はさらにひどい火傷を負っていたことだろう。
かいつまんで言うと - 私は自分を眺めてから、20メートル離れたところに1人の乗務員が立っているのが見えた。彼は外套を着ていたが帽子は被っておらず、その頭と髪はすっかり焦げており、嘆いていた。私は大声で「プルス、あなたですか?」と声を掛けた。彼はうめくように「そうだ」と言った。
私は言った「何てことだ!あなたの姿は!」。彼は答えた「そうなのです。そう言うあなたも・・・」私は自分自身を見ることは出来なかったが、私もかなりひどい格好だった。
そこへ、いつも我々を迎えに来るアメリカ人の友人たちが来て、繋留マストのところに駆け寄り、我々に尋ねた。「一体、どうしたのですか?」だが、それは我々自身にも判らなかった・・・。
それから繋留マストのところに運び、既に用意されていた救急車に乗せた。レークハーストは大きく近代的な空港だったので、救急隊と消防隊がすぐに火災現場に待機していたが、それは大きな助けにはならなかった。
火災発生から燃える飛行船の胴体が墜落するまで、僅か32秒しか経過していなかった。
もっとも、地上支援員と救護隊員は早く現場に来たけれども、彼らは赤々と燃える残骸の50歩先までしか来ることが出来なかった。最後の力で地獄の片隅で命拾いした人たちに、彼らは貴重な援助をもたらした。だが、飛び降りたあと倒れて動かない者や金属の残骸の中に留まった者は帰らぬ人となった。
しかし、多くの人々が脱出してきた。彼らの髪はぼさぼさに乱れていた。どれほど高温であったか想像できる。20万立方メートルの水素が1分程度のあいだに燃焼し、白熱の明るい炎は、その後燃えたディーゼルオイルの黒煙に変わった。
そのあいだに負傷した乗客が運ばれてきた。その中にはドエーナー夫人がおり、とても重い火傷で非常に苦しんでいた。それは見るも恐ろしい情景であった。
私は出来ることなら再び車を降りて救助したいと思ったが、救急車は我々を診療所に運ぶために走り始めていた。2階には、大きな広間に50~60のベッドが用意されていた。私は通路に面した一つを選んだ。
病院の看護スタッフは私を助けようとしたが、私は自分よりもっと重症の怪我人の世話をするように彼らに言った。私は自分で衣類を脱いで下着でシーツにもぐり込んだ。その直後、さらに重傷者が運ばれてきた。そして、その後ローゼンダール司令とアメリカの代理人ウィリー・フォン・マイスターとレーマン船長が着いた。レーマンは、自分がどれほどひどい火傷を負っているかに気がついていないようであった。彼は私のベッドのそばの丸テーブルに座り、この重大な事故の原因について話し合った。
それから、レークウッドのそばの大きな病院に移された。普段は、レークウッドには裕福なニューヨーカーが避暑に来ていた。我々は大きな広間に収容された。そこでは、個々のベッドが帆布のカーテンで仕切られていた。
翌日の4時にローゼンダールが、またやって来て「ザムトちゃん」 -彼はいつも私をそう呼んでいた- 「ザムトちゃん、個室に移ろう!」そこで私は個室で看護を受け、はじめて包帯をして貰った。それは、ひどく火傷していたので難しかった。そこで顔の傷と両手に5ミリ程度 鉛軟膏を塗りつけられ、一対の応急包帯をして貰った。
7時頃、ローゼンタール司令がまた「ザムトちゃん、ニューヨークのハークネス・パヴィリオンに行こう。」と言ってきた。
私は「なぜいま、また移動するのですか、我々はここで申し分ない救護を受けているのに!」と言った。それに対してローゼンタールは答えた。
「いや、そうじゃない。ウィリアム・リーズが我々に無線で、レーマンとプルスと君に、彼の費用負担でハークネス・パヴィリオンの病院に来て貰おうと伝えてきたのだ。」
私は「判りました。彼らが行くなら私も行きますよ。」と言った。
W.B.リーズは以前からのツェッペリン仲間で、世界一周飛行に料金を支払った乗客として同行していた。
2人の看護士が、私をホールの下へと運び出した。
その時まで、まだ頭は覆われており、鼻と眼と耳だけ切り取っていたので、まるでクー・クラックス・クランの様であった。
病院の前にアメリカの多数の報道陣が集まっており、ある建物の屋根の上である男が映写機のハンドルを回しているのを見て驚いた。
そこで私は「何としたことだ、やめてくれ。我々のメンバーと友人たちがドイツでこんな姿を見たら大変だ!」と言った。ヴィリー・フォン・マイスターは「大丈夫です。皆 差し押さえてありますから。何も流されることはありません。」と答えた。
看護士は1人ずつ、キャデラックに寝かせた。
担当が「ちょっと待って下さい。何かあったらこのボタンで非常ベルを鳴らせます。我々は、ほかの人を看なければならないので」と言った。
それから、非常に長い時間が経過した。 - 半時間、一時間、やっと看護士が戻ってきて、出発すると告げた。
ニューヨークから90マイルの通りは交通止めになっていた。
アメリカ人は、皆 遭難した飛行船を見ようと思ったのである。
しかし、我々の運転手は道を切り開いて、警察の支援で雑踏を抜けた。
まもなく我々は、ジョージ・ワシントン橋を過ぎ、セントラルパークに来た。
そこには大きな病院があった。我々はそこで車から降ろされた。
そのあいだに、私の顔は全体的に腫れあがって、右目は見えなくなり、左目もほとんど見えなくなっていた。おぼろげに、私のそばに何人かの白いガウンを着た人が見え、近づいてきた。そしてエレベーターへと入っていった。
ガタンとエレベーターが動き出した。「天国へ行くのですか?」と私は訊ねた。また、ガタンと動きぼんやりと大理石色と金色が見え、私は何処にいるのだろうと思った。
私は長い廊下を車椅子で運ばれていたが、突然ドイツ語の魅力的な女の声で、「まあ、あなたはザムト船長さん?」という声が響いた。私は「はい、人からはそう呼ばれていますが」と答えた。それから大きな天蓋付き寝台のある広い部屋に来た。
そこで私は、まだ多くの白いエプロンとガウンを着た人がいるのに気付いた。
看護婦達や医師達ばかりがいた。そこで、先程と同じ声で「何か飲みますか?」と訊かれた。私は「はい。発泡酒が1杯飲みたい。」と言った。
そう言うとすぐに1本のシャンパンが出てきて、それを小さなガラス管で私に飲ませようとした。私の口は完全に腫れあがっていたからである。
私はそれでもガラス管を口の中に押し込み、それを飲み干した - さらにもう一度注いで、また飲み干した。多分、グラスに3杯か4杯飲んだ。鎮静剤が混ぜてあったのであろう - しかし私はそれに気がつかなかった、とても喉が渇いていたのである。それから私は採血されて、注射を何本か打たれて、それから1、2時間眠り込んだ。
私が目覚めたとき、レーマン船長が死んだという悲しい知らせを聞いた。
レークウッドから搬出される際、とても長い時間車で待たされたときのことであった。彼の火傷はあまりに酷かった。彼の代わりに主任無線士のシュペックがハークネス・パヴィリオンに連れてこられた。しかし、シュペックは - 人はそれに気づいていなかったが - 2重に頭蓋底骨折していた。彼は同じくその夜亡くなった。それでハークネス・パヴィリオンにいるのはプルスと私だけになった。
彼は廊下の反対側に寝ていた。
「ハークネス・パヴィリオン」病院は財団の基金で運営されており、原則的に百万長者のみが扱われていた。そこに何でも揃っていることは、想像に難くない。医師たちは皆それぞれ権威者であり、例えば心臓の専門はグレーデル博士で、彼の父はナウハイム浴場の創設者であった。そこの外科医ウェブスター博士は、不可能とされていた移植を行った。彼は失われた皮膚を焼失した骨から再生した。アメリカのこうした最高の医師たちなくしては、プルスが生命の危機から逃れることは出来なかった。
彼の顔は恐ろしいほど歪んでいた。
鼻は完全に焼失しており、耳はほとんど完全になくなり、眼もひどく損傷していた。手の甲は骨まで焼け焦げていた。プルスはときどき、気温と湿度の調整されていた、いわゆる酸素テントで2~3日過ごした。
大きな移植手術を何度も受け、傷はゆっくりと治療されていった。
私の皮膚は - ありがたいことに - 回復したので、何も処置を必要としなかった。私は、およそ6週間の後、いくらか回復し、客船オイローパで帰国することが出来たが、プルスは移送可能になるまでに、それからさらに4ヶ月も合衆国に居なければならなかった。
惨事の結果は悲しいものであった。
36名の乗客のうち、16の命が失われた。
着陸操船のあいだ窓辺に立っていた多くの人は救助できたが、キャビンでトランクの荷造りをしていた乗客のほとんどに対しては救助が遅れた。
61名のDZR社員(59名の乗組員と同乗していた2人の船長)のうち22名が死亡し、そのほかに1人のアメリカ人地上員が亡くなった。