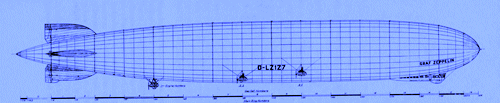
「グラーフ・ツェッペリン」で世界周航
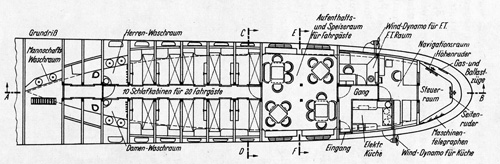
第一区間
船上の会話
ふと見ると、日本人ジャーナリストの北野が片隅で朝の体操代わりに、真面目にチャールストンのソロを夢中になって踊っている。
私は、年配で経験豊富なアメリカの特派員で、ツェッペリンの特別号外を発行することの出来るフォン・ヴィーガント氏に挨拶した。
彼は数日前、東京から帰ってきていた。彼はそこでハースト新聞の支局長としてどんなことでもするつもりであった。彼は気配りの出来る話し好きな人物で、いつも協力的で世界を視野に入れた活動的な人物であった。彼は我々を待ちかまえる歓迎について驚くようなことを言った。しかし、私は感覚的に納得出来ないところがあった。そのとき我々は、まだウルムにすら達していなかったからである。彼が言うところに寄れば日本の当局は空港地域に50万人の人出を想定していた。
飛行船の管理に関しては、ようやく昨日になって緊急報を交信することが出来るようになり、それにより飛行船が充分に保護されるような配慮が行われた。
日本人が感激のあまり羽目を外して、飛行船の周辺で戦争のような大騒ぎをし、歴史的飛行の記念として部品を持ち帰るのではないかと、どうやら彼は心配していたようであった。
それから我々は、フーゴー・エッケナーが一発勝負に出たことによって生じたリスクへの対処を真剣に実行に移した。そうすれば、この飛行船は成功するに違いない!ツェッペリンの方針を頓挫させてはならぬ!
我々の希望という天空に一つの明るい星が昇っていくような感覚を抱いた。
そのとき、フォン・シラー船長が指令ゴンドラから出てきて、英語、フランス語、ドイツ語で次のように伝えた。すなわち、駅も停留所も待合室もない1万キロメートルを超えるこの初飛行では、水を節約するために顔を洗う際には洗面器に小指しか浸してはならぬと。初めて「探検」という重大な言葉が出てきた。
私は窓の外を見た。眼下にドナウの青いベルトが見えてきた。5時半にウルムが見えた。まるで大きな平野をひとっ飛びしているようであった。そのくらいの速さで我々は街の上空を通過した。
堂々とした大聖堂を包む夜明けの中で家々がかわいらしく佇んでいた。
まだ古い壁や美しい運動競技場が見えていたがそれから郊外、そしてまた風景が現れた。ガラスのように明るい朝日を浴びて我々はシュヴァーベンとフランケン地帯を進んだ。7時頃、ニュルンベルクに来た。飛行船はとても順調な飛行を続け、古い街が夢のように背後に消え去って行った。
城塞や旧市街の屋根のうねりが、まるでメリアンの地図のように我々の眼下を通過するのを見ていた。霧はほとんど消えた。窓から差し込む太陽の光が私の顔全体を照らした。わたしはゆっくりメモを取り、手許には一杯のコーヒーがあった。それにしても、なんと不思議なことだろう。まるで、ほんの数分まえに見たニュルンベルクの大きく新しい家々のうちの一つから床や家具や天井で出来た、人間のいる居間が空中へ上がり、空高く走っているみたいだ。