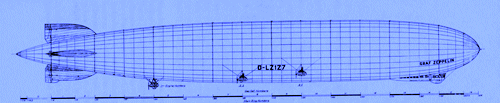
「グラーフ・ツェッペリン」で世界周航

第二、第三区間
離宮にて
天皇に招待された。
世間一般の驚きであった。なぜなら天皇は、この国の統治者であるだけでなく、神であったからである。
彼は日常生活のはるか向こうで人目につかないように宮殿で暮らし、聖人としての尊敬を受けていた。我々が夏の離宮に訪ねたとき、彼は不在であったが、そのことを詫びていた。
我々は最初の静かな庭園を過ぎ、幾重にも曲げて作られた道を通り、小さな橋を越えて、大きな屋根の葺かれた木造家屋の前に来た。
そこには小さな泉庭があり、霧の立ちこめた空が映っていた。
袴を着けた日本人の給仕が、小さな三宝に高価そうな菓子を載せて持ってきた。
野菜のトルテ、氷で冷やした見たこともない果物、お茶、それに煙草や葉巻が載っていた。
体にぴったり合った長い灰色のズボンをはいた二人の漁師が、立派な麦わら帽を被り、頭上に釣り竿を掲げてやってきて、欄干から疑似餌をつけて投げ込んだ。望めば、小魚が食いついたときに竿を引かせて貰えた。
これまで、釣り人が魚を釣り上げることに成功したのをドイツの水域でもそれ以外の場所でも見たことがなかったが、私はここでも一匹も釣れなかった。
しかし、そのことで参謀本部の柴田少佐には良いことがあった。
エッケナーが、彼の金色に輝く肩章の飾り緒を掴んでこう言ったのである。
「太平洋を越えてロサンゼルスまであなたを乗せることにしました。」
その日本人の顔は、春に昇る旭日のように輝いた。そして、エッケナーは軍令部の草鹿少佐にも同じように声を掛けた。
それを聞いて二人の日本軍人は常にぴったりと並んで、目を輝かせ胸を張ってあたりを見渡した。
大臣が呼び寄せられた。陛下に仕える宮内庁長官と閣僚はゆったりと親しみを越えて微笑んだ。