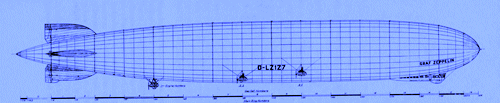
「グラーフ・ツェッペリン」で世界周航

第一区間
真夜中の太陽
その日曜日には、我々の頭がどうなっているのか、時計がどうなっているのか、全く判らなかった。
エッケナーがやってきて、時計の針を3度、4度と振って廻した。太陽は夜になっても沈まなかった。金星が赤く輝いていた。空は朝まで明るいままであった。我々は真夜中でも太陽の沈まない地帯に居たのである。一週間の体験で違う点は、時間が我々のそばを通り過ぎてゆくようであった。普通の人々がこの数週間で体験したことは、我々には時計のように過ぎ去って行った。
8月18日、午後7時の日誌の紙面には次のように記されている。
「我々は今もなお、とてつもない孤独に包まれている。見渡す限り住居はなく、人間の存在も動物も耕地もなく、汗水垂らして働いている人が畑を耕し畝をつけた形跡もない。荒廃した殺風景な丘陵や谷に混沌とした風景が続き、厳しい無限の沈黙があるだけである。凍るような寒気が我々のなかになかったとしても、孤独感に震えた。そこを過ぎてからさらに500キロメートル進んだところに、人間の存在を示す最初の兆候があった。住居である。しかし近くを通ったとき、それは崩壊していることが判った。ここに住んでいた人はその貧しい家からとっくの昔に出て行ったか、あるいはその中で死んでしまったのかもしれない。眠ることにしよう。」
8月19日、月曜日。朝7時、ヤクーツクである。我々はこれまでのことを判っている。相当に航行してきた。
不快な沼地は、まるでタイガの森の下を貫いて続いているように、次々と現れた。まるで再び1000キロメートル引き返してきたかのように、胸を締め付けられる気分になった。水面は広く、大きく、さらに嫌気のさすもののように見えた。
休息できる場所を探して見渡したが無駄だった。そこにあるものは、もはや森ではない森、流れようとしない川、水が水でないために生命を持たない湖。我々は探検することで長い間満足していた。そしてヤクーツクに来た!レナ川に沿って続く果てしない孤独の中に横たわる小さく幅の広い木造家屋と教会が眼に入ってきたような幻覚が見えた。それらは広範囲にバラバラに散らばり、白いブラウスを着た2、3人の人たち。
ゴンドラの前部には、ドイツの戦時捕虜としてシベリアで亡くなった人への追悼のための花環が掛けられた。我々は厳粛な気持ちで上空からのメッセージを伝えた。それはもはや亡くなった我々の戦士だけでではなく、この花環が飛行船から投下されたのを見ている、地上の人たちと我々を初めて結んだ。
それはだんだん小さくなっていった。小さな黒い花環は、墓地のすぐ傍に落ちていった。郵嚢がひとつ、それに続いて投下され、赤い上着を着た人たちがそれをつかみ合った。カルクリンは、ソヴィエトの身分の高い役人に宛てた葉書をそのなかに入れた。郵嚢には全大陸に向けた書状や挨拶状が入っている。それらはいつ届くのであろうか? その道は遠い。そこには、それを速く届けることの出来るツェッペリンはいない。