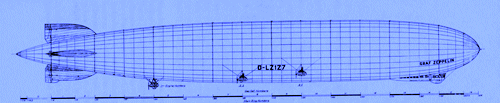
陸を越え、海を越え

Hugo Eckener著 "Im Luftschiff über Länder und Meere"(続き)
南米航路(11)
しかし、突然見たこともない雲塊が飛行船に覆いかかり、見る見るうちにどんどんひどくなってきた。
たとえ無風地帯で驟雨帯に遭遇したときでも、こんな状態は経験したことがなかった。
まもなく巨大な雨粒が雹に変わり始めた。その大きさは胡桃ほどもあった。それが張り詰められた飛行船の外被を太鼓のように叩き始めた。
もう、飛行船が持ちこたえられなくなった。昇降舵手が懸命に高度を維持しようといているのに飛行船は沈降を始めた。谷底から1000フィートの高度から650、500と下がり、僅か300フィートにまでなった。
眼下で谷が微かにきらめいたとき、雹のマントで覆われ、飛行船は12度上向きで飛んでいても、どんどん下がっていった。この仰角は飛行船に最大の動的揚力をもたらすトリムである。
当直についていたフレミング船長が恐ろしげに「博士、エンジンを停めましょうか?」と叫んだ。
「ダメだ!」と叫び返した。「いま、一番必要なのだ! 全速に設定! もしエンジンがダメになったら毎時50~60マイルの速度で地表に激突する。」
指令は実行されたが、高度計の指度はゆっくりと下がり続けていた。
おそらく地表から160~200フィート以下に下がっていたであろう。フレミングに残り2つの貴重なバラスト袋を投下しても良いと言おうとした。その重量は900ポンドであり、少なく見積もっても22000ポンドは重い状態から、何らかの変化を期待することは無理であると思えたが・・。
しかし、ちょうどそのとき昇降舵手が「大丈夫です。飛行船を維持出来そうです。」と叫んだ。
それは事実であった。
飛行船は高度を保持し、やがて徐々に上昇し始めた。
おそらく、エンジンを全開にして2~3百馬力出力させたので、限定された空域の雹混じりの暴風から抜け出せたのだろうと思う。
何れにしても、眼にクマを作ったくらいで抜け出せたが、雷雨を振り返って「もし、何が起こるか予測できたら決してあそこで飛び込むことはなかった!」と思った。
あとでフリードリッヒスハーフェンに帰ってから船体を調べたところ、雹が外被に50個以上の穴を開けていた。間違いなく、氷粒の衝撃が雨の重量とともに船体を沈降させた原因であった。
この同じときに、我々から遠くないところで飛行機が一機、ジェノバとリヨンの間で墜落していた。
雹のなかを飛んでいる10分間、乗客は心配そうにキャビンに座って 外被を叩く太鼓のような音を聞いていたのである。彼らは動転しており、対策をとっていると聞かされていたが、どれほど危険な状態であったかおそらく知らなかったと思う。ただ、ヒューバート・ウィルキンス卿だけは事態を怪しんでいた。この限界状態で、操縦室からエンジンが作動しているか後部を見たが、彼がキャビンから前を見ながら真剣な面持ちで聞きたそうにしているのに出くわした。私が微かに頷くと、彼はそれで事態を理解した。