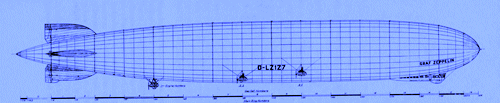
エッケナー博士の夢の乗り物

Douglas Botting著 "Dr Eckener's Dream Machine"
第一章
夢の乗り物
1929年8月15日木曜日、朝の1時である。またの名をコンスタンス湖として知られているボーデン湖に面したドイツ側の街、フリードリッヒスハーフェンのクアガルテンホテルである。湖は静かである。夏の軽い夜風が木立に囲まれた湖畔の街を吹き抜け、月は冴え冴えと輝き、星は空に火花のように散らばっていた。
しかし、静かな夜ではなかった。45歳のドイツの雑誌記者で、フランクフルト新聞の特派員であるマックス・ガイセンヘイナーは、階上の部屋のベッドの中で休みなく寝返りを打ち、階下のパーティの大騒ぎやダンス音楽を演奏するバンド、それに外の砂利を歩く足音と歌や笑い声の騒音のなかで一晩中眠っていなかった。ホテルが、街中が、夜明けのビッグショウを期待して絶え間ない興奮状態であった。フリードリッヒスハーフェンの上流社会がすべてここに集まり、数マイル先からも人々が集まっていた。
階下の明るく照明されたサロンと、広く花で飾られ湖の見えるテラスではフルスイングのパーティが続いていた。ハンサムな、どちらかと言えば物思いに沈んだ若いフランスの新聞通信員レオ・ジュルヴィユ=リーシュは、優雅な顔つきで肌はマホガニ色で -彼の母親は黒人であった- 手摺りに寄りかかり物思いにふけっていた。2~3時間後に彼は、素晴らしい旅に出ることになっていたが、彼は決して帰ってくることはない筈である。パリの ル・マタンで編集長は一ヶ月前に「レオ、君にちょっとした旅をして貰おう」と言ったのである。
ガイセンヘイナーは頭を枕に沈めて闇を見ていた。週の半ばであったが週末のように騒々しかった。世界の半数とも思われる新聞社と、間違いなく重要人物の半数が、その友人達や見送り人とともにお別れパーティに参加していた。そこら中、外国人でいっぱいであった。日本人の夫婦が、月光の中で夜更けの散歩をしており、小柄な夫人は青と白の縞模様の着物を着て下駄で砂利道を歩いていた。彼女は頭を彼の肩に預け、彼の腕は彼女にまわされていた。おそらく、もう二度と逢えないかも知れないと思っているのであろう。堅苦しく非常に礼儀正しいイギリス人の一組がいた。諦めたような、ホームシックにかかった(あるいは2日酔いの)アメリカ人もいた。
ダンサーのように動き回り、何処にでもロザリンという若くて可愛い娘を連れて歩く優雅なフランス人もいた。ロシア人、スペイン人、スイス人、ドイツ人はベルリン在住者や地方から来た人など言うに及ばずであった。何人かは記者であり、それ以外は旅行者であった。スウェーデン国王までも居たし、アメリカの大使も日本の大使もいた。皆、ここに来る理由があった。彼らは世界中から一大イベントを見るために来ていたのである。
ガイセンヘイナーはうたた寝をして、下から響いてくるボストン風ツーステップのリズミカルなビートによって断続的な夢を見ていた。彼は夜勤のポーターに寝室のドアを叩かれて、突然起こされた。「起床時刻です。車はちょうど半時間後に発車します!」
朝の3時であった。出発の時刻である。音楽は終わり、カップルは戻っていた。ホテルのロビーには誰も居なかった。
(工事中)